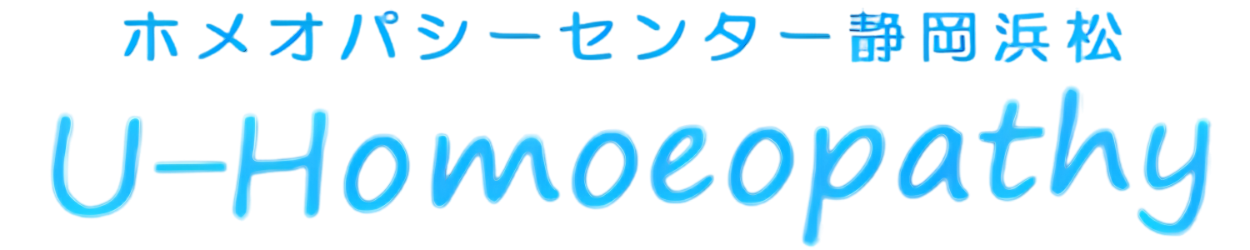ホメオパシーのその歴史や基本原理、レメディーや相談会についての概要をご案内いたします。
ホメオパシーとは?
ホメオパシーは、今から200年ほど前にドイツ人の医師サミュエル・ハーネマンがその生涯をかけて確立した療法です。
Homoeopathy(ホメオパシー)という言葉はハーネマンが作ったギリシャ語の造語です。
Homoios は、「似たようなもの」、Patheiaは、「病気」という意味でこの2つを組み合わせて、Homoeopathy という言葉が誕生しました。

「病気」と「似たようなもの」を与えるため、日本語では、同種療法と訳されています。
例えば発熱した時、ホメオパシーでは熱を下げるお薬ではなく、もう少し熱を上げるようなレメディーを与えます。
すると、身体は「これ以上、熱があがると大変だ!」と自然治癒力を発動させ熱が自然に引いていくのです。
症状は、その時の身体に必要があって起きているのですからホメオパシーではそれを即座に抑えません。
同種の法則
「健康な人に投与して、ある症状を引き起こすものは、それと同じ病状を治す」
一体、どういう意味なのでしょう?
ここで、ホメオパシー誕生の秘話をご紹介します。
ホメオパシーの父ハーネマンは、医師をやめて翻訳家として生計を立てている時期がありました。
ある時、薬の効能がかかれたイギリスの薬効書をドイツ語に翻訳する仕事をしていたのですが、マラリアという病気を治す薬について書かれている 箇所で、はたと考え込みました。

そこには、「キナの樹皮は、その苦味成分がマラリアに効く」 と書かれていました。
しかし、他にも苦い植物はたくさんあるのに、どうしてキナがマラリアに効くのだろう?
不思議に思ったハーネマンは、この植物を煎じて自ら飲んでみました。
すると、発熱、悪寒、虚脱、ふるえなど、まるでマラリアにかかった かのような状態が現れたのです。
周りの知人達に、同じことを試してもらいましたが、 皆同じようにマラリアのような症状が現れました。 しかし、中に一人だけ、実際にマラリアに罹っていた人がいました。 何とその人は、キナの樹皮を煎じたものを飲んだとたん マラリアが治ってしまいました。
健康な人が飲んだら、マラリア症状を引き起こしたキナの樹皮の煎じ薬は、 マラリアにかかっている人にとっては、お薬となったのです。
これが、ホメオパシーでもっとも大切な同種の法則です。
レメディーって何?
ホメオパシーでは、レメディーという小さな粒を口の中で溶かし飲みます。
「口に入れる物だから、安心できないと嫌だなぁ」 と思うのは当然のことです。
でも、レメディーはとっても安全。
このレメディーという粒の原料は、砂糖です。
しかしこの中には、前述のキナの樹皮のような様々な植物や鉱物などから 抽出した成分を、 極微量に薄めたものがしみこませてあります。

希釈倍率は超ウルトラ級で、解析しても成分は存在しません。
だから、たとえ「トリカブト」から作った「アコナイト」というレメディーでも 毒は一切入っていないという訳なのです。
そして、この超ウルトラ級に薄めた溶液を、さらに「振ってたたく」 という作業(振盪)をすると、 植物や動物がもっているエネルギーが 活性化されます。
つまり、原物質のもつ「毒性」は排除し「エネルギー」だけを取り出したものが レメディーなのです。
現在、レメディーは3000種類以上あると言われています。
植物、動物だけでなく鉱物、微生物など、 自然界のあらゆる物質がレメディーの原料となっています。
これらのレメディーを、症状に合わせて選んで行くのが 私たち(ホメオパス)の仕事です。
相談会って何を聞かれるの?
あなたは、どんな症状について困っていますか?
ホメオパシー健康相談会では、あなたの困っていることや改善したい症状について 様々な角度から、質問していきます。
例えば・・・

 あなた
あなた頭が割れるように痛いのです



そうですか。頭痛がするのですね。ところでその頭痛は、いつ頃から始まりましたか?その頃、何か特別な出来事はありませんでしたか?



今年になってからです。新しい仕事について、プレッシャーがかなりありました。



どのようなプレッシャーですか?



失敗するのではないか、上手くできないのではないか、という感じです。



痛みは、どんな感じがしますか?



目が飛び出しそうになって、目を開けていられないんです。
このように、痛みの始まった時期や特徴、それに付随する症状など、細かく聞いていきます。
そして、質問はそれだけに留まりません。
普段からのあなたの体質や、性格、ものの考え方など、今回の痛みとは一見すると 関係ないように思えることも、質問していきます。
あなたは、自分では気づいていなかったような自分の一面を発見することもあります。
こうして、多くの質問をすることにより、あなたの悩んでいる症状に同種の レメディーを 探していきます。
レメディーをとるとどうなるの?
さて、レメディーをとると一体どういう変化が体におきるのでしょう。
レメディーは、いわゆるお薬ではありません。
だから、「これをとったら、こうなる」という、全ての人に共通する改善過程は ないのです。
レメディーの反応は人それぞれ。
よくある変化には、次のようなものがあります。
- 出ていた症状が、上から下へ移動していく
(例:首や顔にあった発疹が、手先、足先へ移動した) - 出ていた症状が、体内から体外へ移動していく
(例:体内の老廃物が体外へ排出される過程で、排尿の量が増えた) - 心から体へ
(例:恐怖の感情を我慢していたが、レメディーを飲んだあと吐いた) - 重要な器官から、より重要でない器官へ
(例:呼吸器官の症状がよくなったが、皮膚にブツブツが出てきた) - 以前患っていた症状が一時的に戻ってくる
(例:何年かぶりに、子供の頃よくかかっていた中耳炎になった)
これらの変化は、「治癒の方向性」に従っています。
体の自然治癒力が発揮され、よい方向に行っていると考えます。
少しの間、つらいかもしれませんが、山を越えるとよい結果が得られます。
何回くらい通うの?
相談会のペースは、理想的には1ヶ月~1ヵ月半に1回のペースです。
1回目の相談会で選択したレメディーが、どのように作用しているかを 2回目の再相談ででしっかりと確認し、他に必要なレメディーを選択していきます。
1度の相談会だけで症状が改善される方も、もちろんいらっしゃいます。 でも、慢性的な問題をお持ちの方は、複数回受けていただく方がよい結果を期待できます。
回数や期間は人それぞれに違いますし、またご本人がどこまでの改善を望んでいるかによっても変わってきます。
初回の相談会の時に、今後の見通しについてお話する時間を設けていますので、お気軽にご質問下さい。